角幡唯介氏のエッセイ集

大きな価値を持つ冒険の対象が、地球上からなくなってしまった。世界最高峰エベレストが人類未踏だった時代や、文明人がアマゾン奥地に足を踏み入れたことが無かった時代ならともかく、世界中で人類の足跡がしるされていない場所があらかたなくなってしまった。日本で冒険における社会的意義が成立していたのは1990年代までだったのではないか。例外的に日本人初8000m峰全14座登頂の竹内洋岳が新聞の1面を飾った。
日本の若手クライマーがヒマラヤの山々で世界的な登攀を成し遂げ、欧米の登山家から賞賛を浴びているにも関わらず、彼らの登山が日本の新聞やテレビで紹介されることはまずない。
もはや冒険は社会から離れ、完全に個人的な行為になった。大きな物語を世の中全体に提示しにくい、個人的な事情から始められる行為に変わったのだ。今や冒険の社会的意義など考えにくいし、そうした理屈を持ち出そうとしても、嘘くさくなって、その試みは破たんしてしまう。
竹内洋岳さんが例外的に大きく取り上げられたのは、冒険が社会全体に共有されていた時代、この人なら出来ると誰もが思っていた山田昇さんら、当時の超人登山家でも達成できなかった記録だからではないでしょうか。
竹内さんが8000m峰全14座コンプリートすることになる2012年のダウラギリ。GPSを使いリアルタイムで位置情報を共有し、カメラマンとして中島健郎さんが帯同、冒険の共有をしています。8000m峰全14座のうち11座が無酸素登頂も日本記録となっている。
角幡が学生時代に読んだというジョー・シンプソンの『死のクレバス』を例に挙げ、
冒険や登山を題材にしたノンフィクションには、遭難からの脱出劇を扱った作品が多い。絶体絶命の危機からの生還は、まぎれもなく非日常の極致であり、一般の人が体験できる類のものではない。しかも、遭難して生き残った一握りの人にしか書けない特殊な体験だ。「死」の世界に片足を踏み込んで戻ってきた一握りの人だけの体験・・・。
冒険をするときは、現場で起こりえるあらゆるリスクを想定して、事前調査をして計画を立てる。命がかかっているので、現場で起こりえるあらゆるトラブルに対応できるように計画を練る。
あらゆるリスクを想定し、いかなる状況になろうとも限りなくリスクを排し、無事に帰還するために。
ジョー・シンプソン『死のクレバス』
冒険の現場で「筋書きのないドラマ」が不幸にも起きた時に、生死に関わる深刻な事態に陥った時に、冒険ノンフィクションの名作が生まれている。しかし冒険は、その深刻な事態に陥る事や、筋書きのないドラマが起きる事を目的とはしていない。もちろんメディアに大々的に取り上げられる事も目的ではない。
ここに冒険そのものの行為と、冒険の記録やノンフィクション作品としての面白さや深さとの間に齟齬が生まれる。
作家となった筆者は、冒険を文章にする難しさと、冒険と職業としての作家は実は相反するのではないか、と苦悩しています。
本を読んだり映像を見ている冒険の観客側にも、「冒険とは何か?」を問う1冊。ノンフィクションのリアルな世界にフィクションが紛れてこないためにも・・・。スポーツ観戦も冒険に触れるのも、そこに本物があるから感動できるのだと思います。
また、冒険を人生と置き換えて、自分自身を見つめ直すきっかけを提案しているとも思える。自己完結と社会の接点、またはその融合や公約数とは何なのか。簡単には結論を出せない命題が、読み手に提示されているようにも感じます。



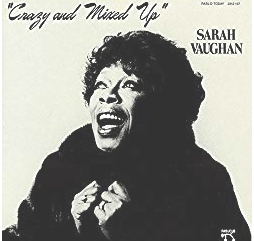
コメント