映画化されてもいいような、時代を反映した良書。

24歳の著者は11歳で父を亡くし、母一人子一人の家庭で育つ。
4年前に母と折り合わず家を飛び出し、なんとなく受けたオーディションにどういう訳か受かり、文学座と俳優座の養成所で、なんとなく真面目に研究生として2年間を過ごす。
その後、芸能プロダクションに所属して、時折テレビや映画に出演しながら、空いた時間はアルバイトや友人と遊び、なんとなく楽しい日々を過ごしていた。
「私は私のやり方で生きる」と家を出て以来、母からの電話をきっかけに4年ぶりの親子の交流が始まる。
執筆当時64歳になる母は「真剣に」和紙彩画に取り組み、著者自身の「なんとなく」と対比させている。
ある日、著者は実家の本棚から1枚の古びた写真を見つける。人々の中心となり、歌っている若い女性の写真。
輝いて見えた。体中から若さを発散していた。大勢の人に囲まれ、写真の中の女性は、凛として輝いていた。
嫉妬と羨望を感じ、輝いて見えた写真の中の女性は、今の著者と変わらぬ年齢の母の姿だった。
当時の母は何をしていたのだろう?
写真の場所はどこなのだろう?
ここから著者の「旅」が始まる。母に説明を求める前に、自分なりに調べ始め「歌声喫茶」というキーワードに辿り着く。今でいえば適切な検索キーワードが見つかって、次から次へと知りたかった情報や資料に手が届いた!といったところ。
僕自身は開口健のエッセイで歌声喫茶を知っていた程度の知識しかない。昔はこんなのが流行ってたんだなと、本書を読むまでは、漠然とした印象しか持ち合わせていなかった。
歌声喫茶
1956年春、西武新宿駅前に開店した灯(ともしび)が発祥。第2次大戦後の時代背景、学生運動や労働運動と共に、うたごえ運動が全国的に広まっていく時代。
街頭テレビで力道山が人気を博し、日本の実質経済成長率が10%を超える。高度経済成長の幕開けの時代に、世相を反映して歌声喫茶は産声を上げた。
ロシア民謡、労働歌、流行歌には無い当時の人々の生活に根付いた歌などが歌われていた。
その全盛期は1960年(昭和35年)前後で、日本各地に200件前後にまで増えた。その後は4畳半フォークの時代、カラオケの時代と、一般大衆の歌の趣向が変わり合唱の時代は終わりを告げる。
歌声喫茶の全盛期には、若者たちが議論を交わすサロンとしても親しまれ、客には作家や画家などの文化人も多かった。当時の若者文化の発信源として、メディアにも注目された。
当時の新聞や雑誌の資料を当った著者は、歌声喫茶を取材した当時の報道を見つける。
・ある日、若い、眼の大きな娘がやってきて、客の歌を導いた。(開口健「ずばり東京」)
・歌声喫茶灯の初代リーダー歌唱指導者水野里矢さん。大きな目に張りのあるアイドル。(週刊朝日)
等々
実家で見つけた古びた写真とシンクロした。「水野里矢は私の母だ!」
母の回想
「終戦から11年、娯楽もなく、人々は戦争で心も体も飢えていた」と母が語る1956年。柴田伸らと共に、歌声喫茶灯を立ち上げ、歌声喫茶一大ブームを作ったパイオニアが母であった。
ロシア民謡のレコードを流す、ロシア料理の大衆食堂から歌声喫茶への業態転換。共に働き、手探りで客と共に歌う店を作り上げていく従業員たち。従業員皆が、店が日々成長していっていることを肌で感じ、充実していた。
著者は、母の若いころを知りたいなら、灯で母と共に時を過ごした人と会ってみたい、という想いを深めていく。
かほるさんとの再会
新装開店間もない灯で、共に歌い、共に働き、共に時を過ごしたかほるさんを母と共に訪ねる。母とかほるさんは20年ぶりの再会となる。当時のアルバムを見ながら、看板娘だった2人は楽しそうに回想を語る。
女性の社会進出がまだ難しかった時代に、何気なく開いた新聞に偶然が宿っていた。
日本登山隊マナスル初登頂成功!石原慎太郎原作太陽の季節封切り!
「私とは関係ないところで、世の中ではいろいろな事が起きている。私には何もない日々が通り過ぎているだけ。」その新聞の求人欄に歌声喫茶灯の募集広告があった。学生時代に合唱団に所属していたかをるさんは、一も二もなく灯に飛び込んでゆく。
1956年5月9日、槇有恒率いる日本山岳会隊の今西壽雄、ギャルツェン・ノルブがマナスル初登頂に成功する。標高8163m、世界8位の高峰に日本人が世界で初めて登頂。
ヒマラヤ初登頂を各国が競い合っていた当時、大手新聞社が登山隊のスポンサーになり、その成果は今では想像つかない程大きく報道される。
世の中全体に受け入れられる明るいニュースだった。記念切手にもなり、一大登山ブームを巻き起こした。
それにしても、登山と全く関係のない歌声喫茶の回想の場面で、マナスル初登頂のニュースが出てくるとは!それほど当時は重大ニュース扱いで、記憶に残るようなニュースだったのでしょう。
「私、マスターに何度注意されても、お客さんの横に座っちゃうの。」
「店が日々成長し、私たちの店、と自覚出来る事が何よりも嬉しかった。生きている実感が、体中から湧き上った。」
歌声喫茶灯創業当時のメニューの1部
カレーライス 60円
ハムサンド 60円
ウォッカ30度 60円
ハイボール 50円
コーヒー 60円
1956年当時の大卒初任給は8700円
母の当時の手帳を頼りに開業当時の常連客や従業員に会う
常連客の1人S
「厳しい時代だから、みんな歌を求めていました。でも、勇気が無くて歌えない。里矢は立派だった。自ら歌って見せて、そして人も歌わせるのだから。」
「それにしても長生きするものですね。まさか、里矢の娘さんと話す日が来るなんて思いもしませんでした。」
ボニージャックス 西脇久夫
「学生時代の当時は、今と違ってマスコミが発達していないから情報が少ない。でも、僕らは情報に飢えている。灯は、遊ぶ場ではあるけれど、客は皆目的や意思を持って来ていた。
自分とは違う境遇の人と語り合える社会大学。新曲がなかなか出てこなかった当時、灯はこんなにいい歌をどこから仕入れてきたんだ、と言いたくなる程に、当時の文化の最先端を進んでいた。」
店で客と共に歌う「灯歌集」は初版1刷10円。第5集まで発行され、改訂版を含めると500万部も発行された。
吉祥寺灯の歌唱指導者 上條恒彦
「ぼくは、いい友人、いい師匠、いいお客さんに出会っていたんだなあ。」「でもね、どんな出会いやきっかけがあったとしても、毎日毎日努力を積み重ねることが大切だと思う。」
創業当初の従業員 ドンちゃん
「長く生きていると、いろんなことが起きるんですね。里矢さんの娘さんが、僕を捜していたなんて。」「人間:人は門を潜ってコミュニティに所属するんですよね。その中で自分は何が出来るか。それだけだと僕は思うんです。人ひとりの力なんて、本当に大したことないんです。」
「人はそうして支え合って生きていく。でも、今はどうかな。私腹を肥やして、都合の悪いことは人のせいにする、そんな人が増えていますね。でも、僕はこれだけは信じているんです。お金でも、地位でもない、人間性が全てだと。」
光と影 不協和音
5坪から始めた灯は、翌年2倍の10坪に拡張。店を広げても収容人数を大幅に上回る客が連日訪れ、店内に入りきらない長蛇の列。時代の先駆け歌声喫茶灯をマスコミがこぞって取り上げる。更に翌年には15坪に店を広げる。
1958年には地下1階地上3階の灯ビルに改装。建設工事の為、店は1年間の休業期間となり、水野里矢とマスターの柴田伸は結婚する。柴田家には勘当されての結婚生活と、店の大幅な拡張が重なる。
店の急成長に合わせて、個人の成長を強いられてきた創業当時からのメンバーが、背伸びを重ねた挙句、息切れを起こし始めてしまう。里矢も疲れ果てていた。
灯ビルが完成すると、1日の来店客数が1000人、2000人となり、世間では「灯からヒット曲が生まれる」と囁かれ、レコード会社から「ステージに立たせてくれ」と歌手や芸人や落語家が送り込まれてくる。
店の拡張と規模の増大と共に、客との間にあった人間関係が薄れてゆく。
経営者であり、夫でもある柴田伸は、次第に店に顔も出さなくなってしまう。そんな中、1962年9月に友人と3人の共同経営で、30坪の吉祥寺灯を開店する。
翌1964年、日本は東京オリンピックに向けてテレビの普及率が高まり、ボウリングブームなどの趣味の多様化、音楽では思想を伴う労働歌や反戦歌から、シャンソン、ジャズ、歌謡曲などが台頭していった。
高度経済成長に支えられた市民は、それらに対応できるだけの経済力を持ちつつあった。
歌声喫茶といえば、1960年をブームの頂点に、その後は穏やかに下降線を辿り、この頃には目に見えて人離れが進んでいく。
従業員の組合活動も活発化していった。
ある意味変質してしまった灯に、心底疲れ切ってしまった里矢は、シャンソン歌手に転身する。
そして1972年に離婚。歌声喫茶灯とも決別する。その後の再婚と出産。極貧生活と父の死別。女手一つで里矢は娘を育てる。
著者は取材を進める中で、どうしても会うことの叶わなかった人がいる。柴田伸、マスターであり母の最初の結婚相手でもある。柴田に会うべきなのか、会っていいものなのか。著者に突きつけられた重い命題となる。
「里矢の娘である私が直接連絡を取ってはいけない。」事情を察している「今でも親交がある」常連客Sを通じても「今は、そっとしておいたほうがいい。」
会わない方がいい。そんな場合もある。
「そっとしておいてあげたい。」周囲の人たちの意見が一致していた。
価値観や文化の先見性があったと見るべきか、戦後の高度経済成長時代に翻弄されたと見るべきか。
また、あまりにも急激な店の成長も原因になってしまったのだろう。
文化や経済の大きな変革の中で、時代を象徴する存在だった歌声喫茶灯。
時代の波に乗り、その波に呑まれてしまった灯。その灯を舞台に強く逞しく生き抜く1人の女性と、その周囲の人たちの、心温まる場面もあれば、胸が引き裂かれそうになることもある。
本書はそんなドキュメンタリーである。



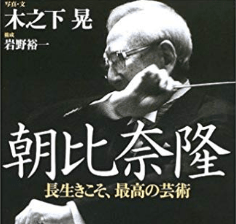
コメント