
K=(1/2)mv²
運動エネルギーは速度の2乗に比例する。速度が2倍になれば衝撃時のエネルギーは4倍に!
UCI会長、仏メディアへのインタビュー
【パリAFP=時事】自転車競技の統括団体である国際自転車競技連合(UCI)のダビド・ラパルティアン会長がロードレースの安全性を高めるため、自転車のスピードを落とすことを検討していると明かした。
ロードレースではこのところ特に下り坂での事故が続いており、一部の選手や主催者からレース中の速度を落とすよう求める声が出ている。その一つの解決策がギア比の制限で、UCIもその選択肢を検討しているという。
ラパルティアン会長は18日に公開された、仏メディアとのインタビューの中で、「年末のどこかの大会でテストを予定している」と明かしつつ、疑念も示した。
「一般的に言って、スピードを落とすのは時代にやや逆行する」「個人的には、ギア比の制限には多くの疑念がある。軽いギアで速くペダルを回す選手や、重いギアでもこげる選手といった持ち味が変わる可能性がある」
「確かにレースは高速化している。特に大きな要因は用具の大幅な効率化だ。ギア比の制限がその解決策になるのか。そう考える人もいる。いずれにせよ、背景にあるのはスピードをどう抑えるかという問題だ」
「難しいのは1レースのテストから結論を出すことだ。ステージレースでも1ステージだけでは検証に必要とするには不足。しかし定義上、統計データを集めるには量が必要だ」
ギヤ比制限はロードレース高速化の抑止力になるのか?
科学的なトレーニング理論の進歩や機材の進歩により、ロードレースは平均時速、最高速度共に年々高速化している。
シマノ製クランクセット(チェーンリング)を例に取ると、完成車組み込みの多くを占めるであろう52×36Tはプロのレースでは全く使われていない。
53×39Tも数年前から使われなくなり、クライマーでもアウター54T。これが最小アウターギヤで55T以上のビッグアウターギヤを使用する選手も多い。
なんと62Tカーボンチェーンリングまで登場!

チェーンリングの大型化、ギヤ比が高くなってレースが高速化したと言うよりも、レースの高速化に対応する為に必要に迫られてチェーンリングの大型化が進んでいると見るべきではないか。
ギヤ比を制限すれば、ロードレースの平均速度の抑制には繋がるかもしれない。しかし大事故になってしまう可能性が高い=速度域の高いダウンヒルやゴールスプリントでの速度抑止にはなり難い。
ダウンヒルやゴールスプリントの高速での集団落車が大怪我に繋がりやすい訳で。
レースの高速化、特に最高速度に関しては空気抵抗の影響が非常に大きい。
ディープリムのホイールに始まって、フレームのみならず機材各部にエアロ化のメスが入る。ウェアやヘルメット、シューズやソックスまでもが空気抵抗を考えて開発される。
ペダルまでもが「前作比で空気抵抗を2%削減」とか。ゆるゆるサイクリストではペダルの空気抵抗2%差は、先ず体感できないであろうに。
競技の世界ではマージナルゲインの積み重ねが進歩や勝利に繋がっています。
機材の軽量化と共に、空気抵抗削減がタイム短縮と高速化の大きな要因であることは間違ってはいないでしょう。
自動車やオートバイなどエンジン付きの乗り物ならば、出力制限やボディ形状をレギュレーションで規制しやすい。
UCI競技規則で機材の規定があるにせよ、今以上に速度を抑制するような規制を設けるのはあまりに非現実的。
進歩や進化を抑えてしまうことになってしまうし、機材を供給するスポンサー各社も難色を示すだろう。
ひとつの例として日本国内で行われる競輪と国際競技であるトラックレース。
ナショナルチームに選抜されている競輪選手の最高速度は、競輪とKEIRINではおよそ10km/hも最高速度が違う。250m周長板張りバンクと競輪場の走路の違いがあるのみで、機材の違いで最高速が10km/hも差がある。
ロードレースも、この時代にクロモリフレームに32Hローハイトホイール、40年も前の機材に規制すれば速度抑制は可能だろうけれども・・・。
受け入れられないだろうし、あまりに非現実的です。
「リムハイトは〇〇mm以下」とか部分的なルール変更なら可能かもしれませんが・・・。
プロテクター着用義務化、ルール化が最も現実的ではないかと個人的には思うところです。

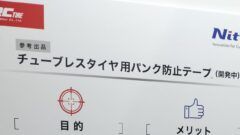

コメント