
スピーカーケーブル比較試聴の経験
昔話になりますが、自宅システムでスピーカーケーブルの比較試聴をしたときの話。
モノラルパワーアンプを使っているので、スピーカーケーブルの銘柄による音質差というよりも、長さを変えるとどうなるかを確かめたくて実験してみたところ、、、
1.MIT Oracle V3.1 (1.5mバイワイヤー仕様)
2.KIMBER 8TC (1.5m)
3.メーカー失念切り売り平行線 ⇒ 上と同じ長さ1.5mからパワーアンプをスピカー直近に設置し徐々に短くしていく
4.自作銀2mm単線 ⇒ 最終的に最短距離の35cmに
(1)のMIT Oracle V3.1見た目の存在感は圧倒的である。高級感といい大蛇のような太さといい、そして何よりもあのデカイ箱があるのだから。
視覚的には2~4を大差で引き離して圧勝である。
プライスタグも、他と比較して1桁多い。重量と音質が比例するなら、太さや見た目で音が決まるなら圧倒的大差。
様々な音楽ソフトをとっかえひっかえしつつ、先ずは1~3の比較試聴をした結果、、、
個人的にはMIT Oracle V3.1に特別な優位性は感じられず。音場感は精密といえば精密ですが、音像の形ははっきりしてはいるが輪郭がぼやける感じがして、何か作為的に作られ整えられた音場に感じられた。
演奏の熱量が若干薄まり、解像度や情報量や細かいニュアンスなども特段優秀とは言えない。
音場の提示を優先した整形美人と言った印象。演奏のパッションが感じられなくなる。
人によっては、このような精巧に作られた”模型”的な音像や音場に惹かれる方もいるかもしれませんが、色彩感というか色数が減っている感じが好みには合いませんでした。
KIMBER 8TCも特段濃厚な方向性のケーブルではありませんが、KIMBER 8TCの方が演奏の細かいニュアンスの違いが聴き取りやすい。
個人的にはKIMBER 8TCの方が解像度が高く感じられた。音場感は提示の仕方に違いはあるが、狭いとか平面的にはならない。むしろこちらの方が自然で作為的に作られた感がしない。
切り売り平行線は、最初に1.5mの同じ長さで試した時は解像度や音場感、音像の輪郭などはKIMBER 8TCが明らかに上。
MIT Oracle V3.1やKIMBER 8TCとの比較では、特定の曲の音色には良さを感じるが、トータルでは色付けがあるようにも感じられました。音場感は精密さには欠ける。
しかし1m ⇒ 50cmと短くしていったところ、この音の変化の大きさに驚きました。
ケーブルの銘柄差以上に、情報量や解像度の違いが感じられたのです。
これはモノラルパワーアンプをスピーカー直近に置いて、スピーカーケーブル最短にするしかない!
最終的にはプリアンプ~モノラルパワーアンプ間は3.5mのバランスケーブル(某専門店オリジナル)。スピーカーケーブルは自作2mm銀単線に落ち着きました。
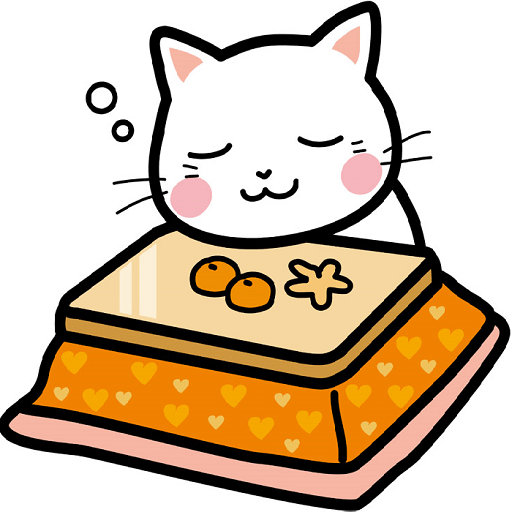
見た目は1番ショボイのに・・・
価格差や見た目の豪華さと、音は全く別々の要素です。
相関関係は皆無。価格や見た目の豪華さと逆転現象が起き、結果としてMIT Oracle V3.1は無駄になってしまいましたが、良い経験になりました。
レーダーチャート
ありとあらゆる製品やお店、サービスがメディアや個人によって評価される時代。
「ブラインドテスト」「フラセボ」「オカルト」がここまで連呼されるジャンルは、オーディオ製品以外に無いと感じる。
レーダーチャートも各項目ごとに採点し相互の関連性は無く、それぞれの項目が独立していることが前提になっています。
僕のもう一つの趣味であるロードバイクでも、見た目のカッコよさや個人的に惚れ込んで買っても、それと実際に使って感じた使用感や製品評とは全く別の話。
値段が高くてカッコイイロードバイクだから、軽くて速くて気持ちよく走れる訳ではない。
工業製品であるからして、車両重量と価格にはある程度の相関関係はあるけれども。
必要な強度や剛性を維持しつつ軽くするには、良い素材を使わなければならないので。
単純に競技のための道具として考えるなら、空気抵抗や路面抵抗などの測定データは存在する。
しかし趣味の道具としてみると、乗り味やフィーリングなどの『気持ちよさ』は感性の領域で数値化に拠る比較は出来ない。
専門メディアの執筆者も読者も、それが分かってレビューを書き読む。カタログスペックや数値だけで比較検討することはない。数字だけのレビューは存在しない。
重量はあるのに走りは軽いホイールなどもありますし。
釣り具でも同じこと。シマノ・ステラとアルテグラの巻き心地を比較している個人ブログに「価格と見た目の高級感に騙されてる!ブラインドテストしろ!」巻き抵抗を「測定しろ!」などと下衆なコメントが付くことはない。
釣り竿を振った感じもほぼ価格に比例するカタログ重量と、振った軽さが比例関係にあるとは限らない。
価格や見た目と、使用感はそれぞれが独立した別々の要素なのだから。
測定しなくても実際に使ってみれば違いが分かること。
オールドABU愛用者も「好き」と機械的な精度や性能とを分けて評価しているし、短所も理解した上で愛用している。
和竿でも塗りや仕上げの美しさと釣り味の使用感は、相関関係の無い別の話だ。
ロードバイクも釣り具でもスペックから予想していた使用感を良い意味で裏切ってくれる、良い製品に出会えると嬉しいものです。
コスパ良くて耐久性があれば尚のこと。
『音』という目に見えない抽象だからなのだろうか。オーディオ機器の評価評論に対してだけ、他の製品やサービスとは異なる捉え方をされてしまう。
個人個人で製品の使用感や感想に違いが出ることはありますが、オーディオ評論程オカルトだの洗脳などと騒がれるジャンルは無い。
オーディオ製品は電子機器であるが故に、測定値はロードバイクや釣り具など他の趣味の道具よりも詳細で多岐に渡って公表されている。
クラシック音楽のジャンルでは美人演奏家に一定の需要があるのだけれども、容姿と演奏は別の話だし評価軸が根本から違う別なもの。
食のジャンルでも、お世辞にも綺麗とは言えない庶民的な定食屋さんで味は抜群とか、接客態度は丁寧とは言えないけど味は良い頑固おやじがやってるお店とかあるし。
味の良し悪しと接客やら店構えは分けて考える。
あらゆるジャンルの中で、オーディオ評論だけが独特の評価に晒されている。
数字だけしか信用しない層が一定数存在している特殊なジャンルがオーディオです。
オーディオ雑誌や評論家にもさまざまあって、売らんが為の商売屋とオーディオや音楽を文化と捉えた、評論というよりも文学として読むべきオーディオ評論があったりする。
ステルスマーケティングは2023年10月1日より景品表示法違反となった。これに習って、メーカーから金銭を受け取っている試聴記事は「PR」と表記すべきではないかとは思うところはあるけれども。
認知バイアスとブラインドテスト
ワインのブラインドテイスティングや日本酒の利き酒などに、ブラインドテストが存在しています。
大会や勉強会なども頻繁に開催されていて、オーディオ機器の評価評論よりも遥かに発展しています。
僕自身お酒は飲めないので知識は全くありませんが、マイナーなオーディオ趣味よりも遥かに理論的に系統立てられて確立されているのは理解できます。
『ブラインド』について、なるほどな~と納得した考え方を紹介します。
ブラインドで間違える原因は、そもそもその品種を知らない場合を除けば思い込みがほとんどの要因だと思っています。
ブラインドでは自分に生じる認知バイアスとの闘いと言っても過言ではないと思っています。自分にとって好都合な情報を優先したり、自分の先入観の裏付けとなるような情報だけを集めようとすることは「確証バイアス」と呼ばれます。
バイアスに惑わされない為には「人の意見に耳を傾ける」「批判的視点(多角的な視点)を持つ」「事実と意見を分ける」「自己の判断軸を確立する」等が挙げられていて、学びがあります。
もう1度繰り返すと、
ブラインドは自分に生じる認知バイアスとの闘い
あくまでも自己研鑽。オーディオ界隈で連呼される「ブラインドテスト」や何でもかんでもフラセボやオカルトとしてしまう事に対する違和感はここにありました。
リアルでは聞かないのにSNSや掲示板などインターネット上では連呼されている。
違和感は自分自身の内面ことを外に向けて発信しているからだったのだ。
確かにオーディオ評論家の表現やレビューに、針小棒大に感じたり忖度あるんじゃと感じることもある。
それらを踏まえて「他人の意見に耳を傾ける」ことになるし、同じ機材を試聴して「ここは同じ意見だけど、ここは意見が違うな」等で自身の鍛錬にもなるし、その評論家の表現方法の傾向もつかめてくる。
自室で行う極々プライベートなオーディオ趣味ではあるけれども『認知バイアス』に捕らわれないように、人の音を聴いたり試聴会に出向いたり感想を交換したり・・・コミュニケーションも大切なのだなと再確認した次第です。

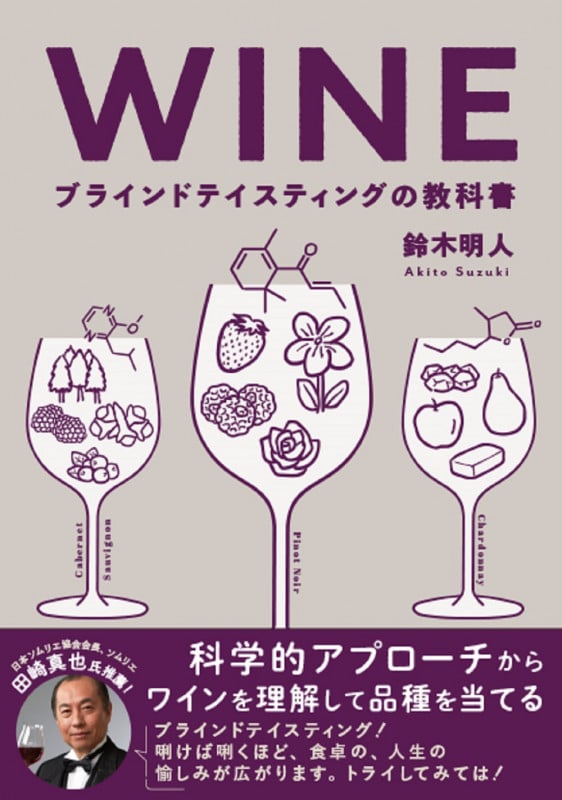
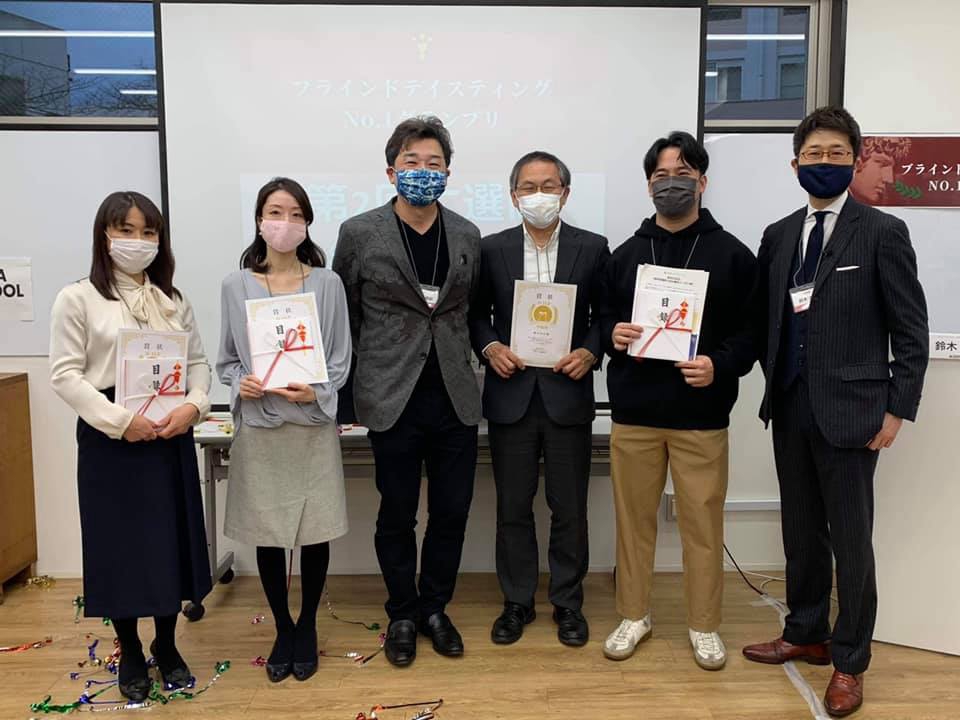
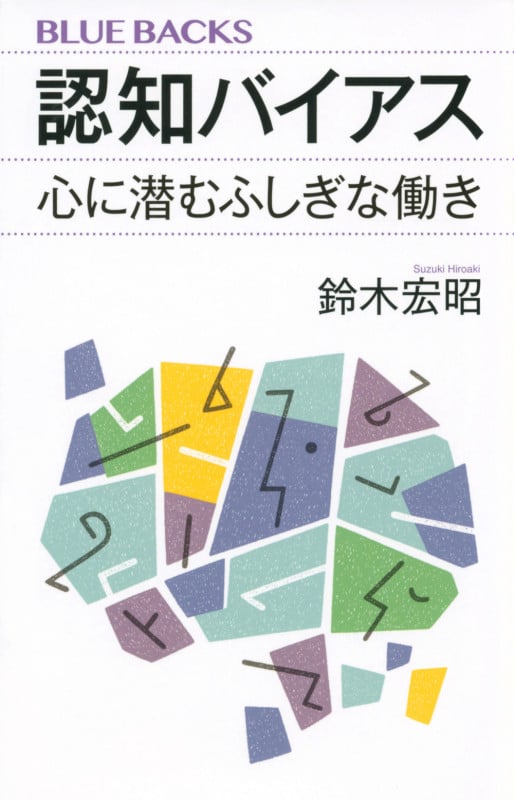

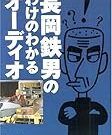
コメント